- トップページ >
- 市政情報 >
- 政策・財政 >
- 市政について >
- 社会保障・税番号(マイナンバー)制度 >
- マイナンバー制度について
ページの本文です。
更新日付:2025年9月17日 / ページ番号:C052672
マイナンバー制度について
マイナンバー制度について
マイナンバー制度は、デジタル社会の基盤として、国民の利便性向上と行政の効率化をあわせて進め、より公平・公正な社会を実現するためのインフラです。マイナンバー制度における行政機関等の間での情報連携により、各種の行政手続における添付書類の省略などが可能となります。
なお、マイナンバーは、住民票を持つ日本国内の全住民に付番される12桁の番号です。
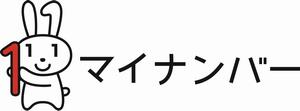 |
| デジタル庁:マイナンバー制度とは(新しいウィンドウで開きます) |
情報連携について
情報連携とは、行政機関等同士が専用のネットワークシステム(情報提供ネットワークシステム)を用いて、行政手続に必要な情報をやり取りすることです。
これにより、市民の皆様が、各種行政手続での書類提出を省略することが可能となっています。
マイナポータルについて
子育てや介護など、行政手続のオンライン窓口です。オンライン申請のほか、行政機関等が保有するご自身の情報の確認や、行政機関等からのお知らせ通知の受信などのサービスを提供します。
 |
| デジタル庁:マイナポータルの紹介(新しいウィンドウで開きます) |
マイナンバー制度に便乗した詐欺への注意喚起について
消費者庁:マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘や個人情報の取得にご注意ください!(新しいウィンドウで開きます)
消費者庁:消費者ホットライン(新しいウィンドウで開きます)
独立行政法人国民生活センター:マイナンバー制度に便乗した不審な電話等にご注意ください!(新しいウィンドウで開きます)
警察庁:特殊詐欺対策ホームページ(新しいウィンドウで開きます)
お問い合わせ先について
マイナンバー制度に関するもの
デジタル庁:マイナンバー制度に関するお問い合わせ(新しいウィンドウで開きます)
マイナンバー総合フリーダイヤル
0120-95-0178 (フリーダイヤル)
受付時間:平日9時30分から20時00分まで、土日祝9時30分から17時30分まで(年末年始(12月29日から1月3日)を除く)
受付内容:音声ガイダンスに従って、該当する音声案内番号を選択してください。
1番:マイナンバーカード・電子証明書・個人番号通知書・通知カード・コンビニ等での証明書交付サービス
2番:マイナンバーカード及び電子証明書を搭載したスマートフォンの紛失・盗難
3番:マイナンバー制度・法人番号
4番:マイナポータル及びスマホ用電子証明書
5番:マイナンバーカードの健康保険証利用
6番:公金受取口座登録制度・預貯金口座付番制度
7番:マイナ免許証
マイナンバーの取り扱いに関するもの
個人情報保護委員会:マイナンバー苦情あっせん相談窓口(新しいウィンドウで開きます)
03-6457-9585(通話料金がかかります。)
受付時間:9時半~17時半 (土日祝日及び年末年始を除く)
関連リンク
この記事についてのお問い合わせ
都市戦略本部/デジタル改革推進部 デジタル改革担当
電話番号:048-829-1047・1048 ファックス:048-829-1985