- トップページ >
- 市政情報 >
- 平和・人権政策・男女共同参画 >
- 男女共同参画推進センター >
- 講座・イベントに参加するには >
- 令和6年度 >
- 【報告】令和6年度ライフキャリア講座
ページの本文です。
更新日付:2024年12月25日 / ページ番号:C118459
【報告】令和6年度ライフキャリア講座
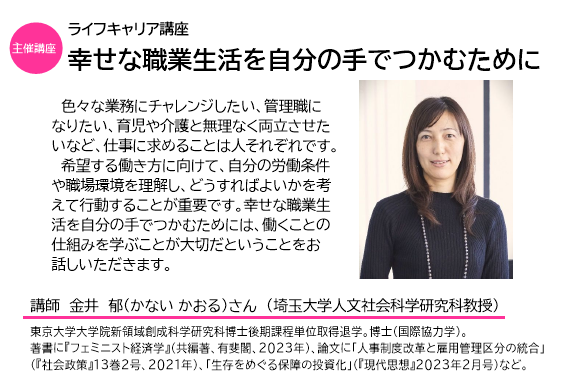
|
日時 |
テーマ |
講師 |
|
12月15日(日) |
幸せな職業生活を自分の手でつかむために |
金井 郁 さん (埼玉大学人文社会科学研究科 教授) |
講義内容
・人間が生きる社会を持続するためには
人間は誰しも、成長段階・病気・老い等でケアを必要とする。
無償のケア労働は主に女性が担っており、そのことに対する社会的評価にも関わらず、社会的責任とみなされている事実がある。
・持続可能な社会とケア
コロナ禍で社会的ケア供給が削減されると、それを女性が無償で担うことで代替された。例えば学校が休校になったことで必要となった子どもの世話を女性が仕事を辞めたり減らしたりして担うことになった。また、看護師・介護士の不足にも陥り、人々の命も脅かすことに。
・労働市場における格差と企業
人手不足の中、女性の就業率は急増しているが、正規・非正規の処遇格差、ジェンダーによる偏りが大きい。そのため、男女間賃金格差も大きく、女性管理職比率が低い。これは、女性はアンペイドワークを担っているため、企業が求める働き方(長時間労働可、転勤可等の企業拘束度の高い働き方)ができないことによる。
また、企業拘束度の高い働き方でないと処遇が高くならない設計になっており、企業拘束度が高い働き方が出来ない人は、そうでない働き方を「自由に選択できる」という体を取っているため、ケアを担う人は有償労働での不利を背負わされる。
・国際社会との比較
どの国でもペイドワークとアンペイドワークの時間負担は男女で5:5ではなく、完全な平等が実現している国はないが、日本の男性の少なさは突出。このことが、日本のペイドワークにおける女性の不利をもたらしている。
・「幸せな職業生活」を実現するためには
中核的労働者の長時間労働の規制により、すべての人がケアを担える労働時間に見直す(企業拘束度が高いか否かということによる選択肢の拡大ではない)。
男女間及び正規・非正規賃金格差を是正する法政策を見直す。
変革主体が誰なのかということは難しいが、社会全体で考えていきたい。
受講者の声
・ありがとうございました。先生のおっしゃる通り、やはり男性の労働時間を変える必要があると思います。夫は転勤族、長時間労働な為、ケアの時間がほとんど取れず、結果私がケアの全てを担う状況です。ケアの時間も十分に取り、幸せな職業生活を送ることができる世の中になって欲しいです。
・一企業としての考え方ではなく、一社会として労働のデコボコを担うという外国の考え方、いいなあと思った。視野の広い考え方を持てる人に子供を育てていくべきだと感じた。ありがとうございました。
・働く主体(労働者として権利をもっている)であることを私たちは忘れているというか、そもそも考えたことがあるのだろうか。目先の賃金やとりあえずの権利獲得ばかりに目がいっていないか、と思った。
講座風景
 |
 |
関連ダウンロードファイル
この記事についてのお問い合わせ
市民局/人権政策・男女共同参画課/男女共同参画推進センター
電話番号:048-643-5816 ファックス:048-643-5801
 11月募集(PDF形式 760キロバイト)
11月募集(PDF形式 760キロバイト)