- トップページ >
- 市政情報 >
- 平和・人権政策・男女共同参画 >
- 男女共同参画推進センター >
- 講座・イベントに参加するには >
- 令和6年度 >
- 【報告】令和6年度アートから学ぶジェンダー
ページの本文です。
更新日付:2024年10月4日 / ページ番号:C117034
【報告】令和6年度アートから学ぶジェンダー
|
日時 |
テーマ |
講師 |
|
9月11日(水)~20日(金) |
近年変化するアート業界のジェンダー意識 |
小田原 のどか さん(彫刻家) |
講義内容
・人権の歴史を考える上で「ジェンダー」の視点は人権史上の大発見という言われ方がある。人権は市民革命を機に形づくられたが、その概念が立ち上がった時の権利の主体は男性のみで、遅れて女性も同等の権利があると主張している。ここにジェンダーの視点が発見される。ジェンダーは社会にとって重要な視点だが、ギャップをどのように解消するのかは喫緊の課題。
・アート業界のジェンダー意識はどんな風に変わってきたのか。
リンダ・ノックリン「なぜ女性の大芸術家は現れないのか?」という論文の問いから考える、定義の偏りや不平等から起こる不都合について。
講師が参加している色々なジャンルの表現者からなる団体「表現の現場調査団」の行った調査結果「ジェンダーバランス白書2022」では、あらゆる分野での偏り不均衡が見られる。そこから導き出されるジェンダーの不利益について。
美術業界のジェンダーギャップが背景にある、ギャラリーストーカーの問題について等。
・彫刻にジェンダーの視点を投入すると、人間が変化を実現できる力の現れを感じ取ることができる。彫刻は我々の変化を鏡写しにしている。
受講者の声
・「なぜ女性の大芸術家は現れないのか」というリンダ・ノックリンの論文のお話、ヨハン・ゾファニーの絵「王立アカデミー会員たち」、とても面白かったです。表現の現場調査団のジェンダーバランス白書のお話を聴き、評価する仕組みに男性が圧倒的多数な中で「いい作品」が決められていく現実を知りました。広告や宣伝に惑わされず、自分の目で作品を観ようと思いました。彫刻ももっと観てみようと思います。よい気づきをいただき、ありがとうございました。
・アート領域のジェンダーギャップに関して、あまりにも無知だったことが分かりました。自分自身の姿勢も、芸術という少し特殊に思える世界だったためか、ちゃんと見ていなかった、細かなことに気が付かなかったためだと深く反省しました。大きな気づきをありがとうございました。
・小田原さんの評論に以前から興味があったので、とても楽しく視聴しました。一回かぎりではなく、複数回に分けてもっと聞きたい!と思うくらい良かったです。
性差別的な日本に暮らしていると、正直なところ、今なお「女性を権利の主体として想定していない」フランス革命時とたいして変わらないのではないかと辛くなることが多々あります。しかし、小田原さんが講義終盤におっしゃった「人間の可変性」という言葉に希望をもらいました。アート界の構造、ひいては社会全体の構造が、少しずつでも性差別的でないものに変化することを期待し続けたいです。どうもありがとうございました。
関連ダウンロードファイル
この記事についてのお問い合わせ
市民局/人権政策・男女共同参画課/男女共同参画推進センター
電話番号:048-643-5816 ファックス:048-643-5801
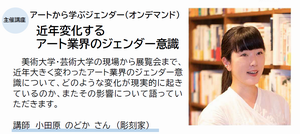
 8月チラシ(PDF形式 694キロバイト)
8月チラシ(PDF形式 694キロバイト)