- トップページ >
- 市政情報 >
- 平和・人権政策・男女共同参画 >
- 男女共同参画推進センター >
- 講座・イベントに参加するには >
- 令和7年度 >
- 【報告】令和7年度メディア・リテラシー講座
ページの本文です。
更新日付:2025年10月9日 / ページ番号:C124992
【報告】令和7年度メディア・リテラシー講座
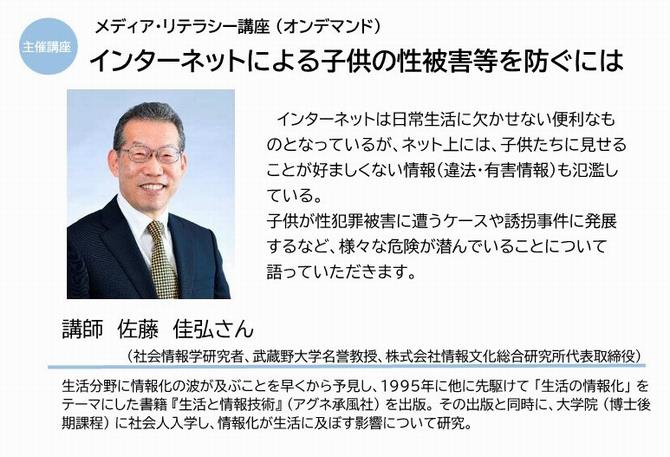
|
日時 |
テーマ |
講師 |
|
9月10日(水)~19日(金) |
インターネットによる子供の性被害を防ぐには |
佐藤 佳弘さん (社会情報学研究者、武蔵野大学名誉教授、株式会社情報文化総合研究所代表取締役) |
講義内容
〇ネットに潜む危険
危険は60以上ある。3つに分類することができ、それぞれに20以上の危険がある。数ある中から子供たちの性被害に関わるものを紹介。
1.ネットを悪用した犯罪
ストーカー、自画撮りの提供、連れ回し、フェイク等がある。
子供はSNSで知り合った人を簡単に信用してしまう。友達作りがネット利用の目的の一つとなっており、同じ趣味の人に悪い人はいないという心理が働く。
2.ネットでのトラブル
自画撮りの掲載、写真無断投稿等がある。
今まで無事だったのは、ただ運が良かっただけ。
多くの子供が自ら個人情報を掲載している。子供たちは「危険だ、駄目だ」と言うだけでは伝わっておらず、被害事例を合わせて紹介する必要がある。
3.人体・健康への懸念
正しい姿勢・適切な時間で使うならスマホもネットも生活を助ける便利なもの。「悪い姿勢」と「使い過ぎ」が健康被害を引き起こす。
〇被害の未然防止(保護者にできることを紹介)
1.話しておく、決めておく 2.フィルタリング(有害サイトアクセル制限) 3.ペアレンタルコントロール4.LINEの設定。
子どもは大人の背中を見ている。身近にいる大人が正しく使うことが大事。
〇被害にあったなら(保護者にできる対処について)
まずするべきは何もしない、無視すること(スルースキル)。 無視できなければ「法的措置をとります」と警告する。相談先に伝わるように記録の保存をして証拠を残す。
子供の被害であれば学校に連絡することも必要。教育上の指導で解決すればここまで。
犯罪性があれば警察に通報する。重大な人権侵害ならば、ネット被害の専門窓口に相談、削除の申し出をする。
削除は難航する。それでもなんとかしたいならば裁判所の手続きになり、覚悟が必要となる(弁護士費用、手続き、時間、精神的苦痛等)。そのため多くは泣き寝入りが現状。
受講者の声
・一般的に言われている内容が多かったと思うが、対策について具体的に示してもらえたのはよかった。
・携帯のトラブルや人権侵害になる項目を理解できました。
関連ダウンロードファイル
この記事についてのお問い合わせ
市民局/人権政策・男女共同参画課/男女共同参画推進センター
電話番号:048-643-5816 ファックス:048-643-5801
 8月募集(メディア・リテラシー講座)(PDF形式 717キロバイト)
8月募集(メディア・リテラシー講座)(PDF形式 717キロバイト)