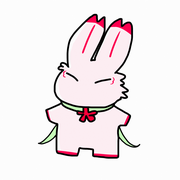|
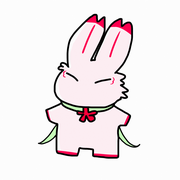
文化財キャラクター「サクラソウサギ」
|
田島ケ原サクラソウ自生地 サクラソウ開花状況(2023年)
田島ケ原サクラソウ自生地は、サクラソウ自生地として唯一の国指定特別天然記念物です。
サクラソウをはじめ、多くの植物が自生し、四季を通して様々な花を見ることができます。
自生地のサクラソウは、3月下旬頃に咲き始め、4月上旬に見ごろを迎えます。
4月27日
サクラソウは二次指定地南側でわずかに開花したものが見られる以外は、ほとんどの場所で開花が終わっており、果実が成長する時期に
なっています。オギやヨシの根元を観察すると、サクラソウの葉が観察でき、成長中の果実も観察できます。
サクラソウの葉は、この後もしばらく残って根茎に栄養を供給し続けます。果実は熟すと種子を散布し、次世代につなげます。
サクラソウ以外の植物では、チョウジソウ、レンリソウが引き続き見頃で、しばらく開花を楽しめそうです。
ウシハコベの開花が目立つ様子も見えるようになっています。ウシハコベは、1年を通して少数は開花が見られる植物ですが、
多くの花が目立つ様子から今が開花のピークであることが感じられます。
サクラソウ同様、開花の時期から果実の時期になっている植物もあり、
アマドコロでは、開花した花も依然多くみられますが、若い果実が開花の終わった花被を破って膨らんでいる様子も観察されます。
ノウルシでは、果実が茶色く熟しているものが見られる他、黄色く変わった葉のものも出てきており、生育期の終わりを感じさせます。
今後の開花に向けて、成長する植物もあり、
バアソブはつるを伸ばして、オギに登っている様子が観察できます。バアソブのつるは、葉が4枚セットについて、毛が生えている様子が
特徴で、このあとベル型の特徴的な花を咲かせます。
昆虫では、引き続きジャコウアゲハの飛翔が見られる他、ハムシやカミキリムシ、ゾウムシの仲間、昼行性のガの仲間など、多くの種類が見られ、賑やかな季節が続きます。
2月から更新を続け、サクラソウの開花状況と自生地の様子をお伝えしてきましたが、サクラソウの開花がほぼ終了したので、
今年のサクラソウ開花状況の更新はこれまでにしたいと思います。来年も引き続きサクラソウの開花や春の植物などに出会えることを願っています。サクラソウ自生地では、この後も様々な植物の開花や昆虫などが見られるので、今後も気にかけていただけると嬉しいです。

二次指定地南側のサクラソウの花 |

オギやヨシの根元のサクラソウの果実 |

チョウジソウの群落 |

レンリソウの花 |

ウシハコベの花 |

バアソブのつる |

ジャコウアゲハのメス |
4月20日
サクラソウの開花は終盤で、柵沿いから見える場所は数少なくなってきましたが、丈の高い草の間をよく観察すると
花を見られる場所もまだ残っています。第二次指定地南側では、引き続き開花が見られる場所があります。
サクラソウ以外の植物では、引き続きチョウジソウが見頃で、いくつか固まって開花している場所があります。開いている花が多くなり、
蕾が少なくなってきました。
その他目立つものとしては、レンリソウが見頃になってきています。レンリソウは、サクラソウやチョウジソウのように花を密集してつける植物ではありませんが、
点々と多くの花が開花している様子が観察されます。
ヘビイチゴ、ヤブヘビイチゴは開花後のものが目立つようになっていますが開花が見られ、ヘビイチゴでは赤くなり始めの果実が観察されました。
ヤエムグラは、微小な緑色の花をよく咲かせ、未熟な果実も多く見られます。ハナムグラはまだ開花しておらず、
成長中で、葉の艶めきが増していっています。この後、開花すると近縁のヤエムグラとは異なり、白い花が見られます。
ノウルシは果実が黄色くなったものが見られるようになってきました。種子の成熟が進んでいることが感じられます。
ツボスミレは、3月27日にも紹介しましたが、現在も引き続き開花中です。3月に紹介した時よりも茎が長くなり、立ち上がりながら開花を続けています。
その他、ツメクサの開花を観察できました、小さな花が園路近くに開花しています。
昆虫では、アマドコロに訪れるシロスジヒゲナガハナバチが観察されました。サクラソウにも訪花していたヒゲナガハナバチ類ですが、
アマドコロにも訪花しているようです。
他にも、花の上を観察していると、ヤブキリの幼虫が乗っている様子もよく見かけるようになってきました。写真はチョウジソウに乗っているヤブキリの幼虫です。

サクラソウの花 |

草の間に見えるサクラソウの群落 |

チョウジソウの花 |

レンリソウの花 |

ヘビイチゴの果実 |

ヤブヘビイチゴの花 |

ヤエムグラの花 |

成長中のハナムグラ |

ノウルシの果実 |

ツボスミレの花 |

ツメクサ |

アマドコロに訪花するシロスジヒゲナガハナバチ |

チョウジソウの上に乗るヤブキリ |
4月16日
4月16日は「さくら草まつり’23」が開催され、多くの人が自生地に訪れていました。
サクラソウは開花終盤で、伸長するスイバやコバギボウシなどの陰になりながら点々と開花するものが見られる他、
少数の固まって開花する群落がみられました。
二次指定地南側では、サクラソウも開花したものがまだあり、しばらく楽しめそうです。
サクラソウ以外の植物では、チョウジソウの開花が盛んで、自生地内の複数の場所で見ることができます。まだ開花前の蕾も多く、
まだまだ開花を楽しめそうです。エキサイゼリも成長の早いもので開花が始まった様子で、白く細かい花が見られました。
ウシハコベの開花も見られ、大きく育った茎の先端に小さな花をつけています。
その他、自生地内では、初夏から夏に向けての植物の成長が盛んで、オニユリも大きく成長している様子が見られました。
昆虫の活動は引き続き活発で、引き続きヒゲナガガの一種も見られました。今回は触角の短いメスも確認できました。
飛翔する昆虫以外にも、今回はマルクビツチハンミョウが観察路を歩いている様子が確認できました。
ツチハンミョウの仲間は有毒な分泌液を出しますが、触らない限り害がなく、また埼玉県のレッドリストにも挙げられている生物なので、
大きな腹部を引きずって歩く姿を見守っていただけると嬉しいです。
また、飛ぶことができないので、踏まないように注意していただけると幸いです。

「さくら草まつり’23」開催中の自生地の様子 |

コバギボウシなどの間から開花するサクラソウ |

まだ固まって開花が見られるサクラソウ群落 |

二次指定地南側のサクラソウ群落 |

チョウジソウの花 |

エキサイゼリの花 |

ウシハコベの花 |

成長中のオニユリ |

ヒゲナガガの一種(♀) |

マルクビツチハンミョウ |
4月11日~12日
サクラソウは、強風で傷んだ花や、すでに散っている花が見られるようになってきましたが、
新たに開いた花もあり、群落がみられる場所も残っています。周囲の植物の伸長も進んでおり、
陰になっている花が目立ちます。一方、白いサクラソウは蕾もあるような状態で、もうしばらく楽しめそうです。
自生地全体は、スイバの穂が一面に広がって薄っすら赤色を帯びていて、ノウルシの黄緑色一面の様子から移り変わったことが
感じられます。
ハナムグラや、ノジトラノオ、オカトラノオなどの初夏に開花する植物も大きくなってきており、次の季節の兆しも
感じることができます。
早い時期から姿を見せていたヒロハハナヤスリは、胞子葉が成長し、胞子を飛ばす時期も近いようです。
チョウジソウは開花を始めており、青っぽい花の群落がみられる場所も多くなってきました。
11日~12日は、汗ばむような陽気で、昆虫の活動が活発にみられました。日差しの中、ジャコウアゲハが飛翔する様子も見られました。
ジャコウアゲハはウマノスズクサという植物に産卵するので、自生地内の芽吹きだしたウマノスズクサを探しに来ている
のかもしれません。
足元あたりの低い場所では昼間活動するガの一種であるヒゲナガガの仲間も見られました。ヒゲナガガはごく小さい昆虫ですが、
羽は光沢のある鱗粉でおおわれており、日の光を受けて輝きます。体長よりはるかに長い触角を広げて飛翔する様子はとても特徴的で、
浮遊しているような錯覚を覚えます。

伸長中の植物の間から見えるサクラソウ |

開花中のサクラソウ群落 |

開花中の白いサクラソウ |

スイバ群落 |

ハナムグラ |

ノジトラノオ |

ヒロハハナヤスリ |

チョウジソウの花 |

ジャコウアゲハ |

ヒゲナガガの一種 |

ヒゲナガガの一種が飛翔している様子 |
4月5日~6日
5日は、日差しがまぶしい陽気で、6日は、にわか雨が降っていましたが日差しが差すタイミングも多くありました。
サクラソウは満開の状態で、密集したサクラソウ群落がいくつかの場所で見られます!
しかし、オギやスイバなどの植物の伸長が進んでおり、サクラソウが陰になっている場所が目立ってきました。
サクラソウのピンク色が一見してわからないような場所でも、陰を観察するとしっかりと開花したサクラソウが
見られるかもしれません。
サクラソウ以外の植物では、アマドコロの開花が始まっていて、垂れ下がるようにして開花する、白と緑色の花が観察できます。
また、トダスゲも開花している様子が観察され、茶色いおしべが見えます。
小さな花では、ハナイバナやヘビイチゴが開花していて、足元をよく見ると観察できます。
昆虫の活動も引き続き活発で、ベニシジミなどの蝶の仲間が飛翔する様子が見られたり、サクラソウにヒゲナガハナバチ類が訪れる
様子も確認できました

密集したサクラソウ群落 |

オギやスイバの陰のサクラソウ |

アマドコロの花 |

トダスゲの花 |

ハナイバナの花 |

ヘビイチゴの花 |

ベニシジミ |

サクラソウに訪れるヒゲナガハナバチ類 |
3月27日
サクラソウが群れて開花する場所が目立ってきました!
まだ蕾のものもあり、もう少し開花する範囲は広がりますが、開花が進んでいるところが目立つように
なってきています。
サクラソウ以外の植物では、アマドコロの出芽が目立つようになってきています、まだ蕾は葉の中です。
また、ツボスミレ、アリアケスミレが見られるようになってきました。通路沿いに開花している場所が多いので、足元を探すと小さな花が見つかります。
足元から頭上に視線を移すと、樹木の変化も見られます。
自生地内では、クヌギの開花が始まっています。黄緑色の垂れ下がった花が特徴的な雄花が目立ちます。雌花は小さく見つけにくいですが、実ると大きなどんぐりになります。
桜草公園の桜も開花し、自生地内の景色と合わせて春特有の景色を見ることができます。
植物以外の活動も活発になり、ノウルシなどにはハチなどの昆虫が訪れる様子が目立つようになっています。

サクラソウの群落 |

サクラソウの花 |

アマドコロの出芽 |

ツボスミレの花 |

アリアケスミレの花 |

クヌギの花 |

サクラの花と自生地 |

ノウルシの花に訪れる昆虫 |
3月22日
サクラソウの開花が進んできています。
開花した株が集まった場所も見られるようになってきました。
ノウルシは見頃を迎えており、自生地全体を黄色く染めています。
3月14日時点ではまだ見頃のものも多かったアマナですが、開花はそろそろ終わりになっており、散り始めから開花終わりの花が目立つようになりました。
一方で、前回開花が確認できたジロボウエンゴサクは、開花の確認できる場所が増え、今回は、ヒキノカサ、ミツバツチグリの開花が
新たに確認できるなど、季節の移り変わりを感じることができます。
その他にも、カキドオシの花や、ヒロハハナヤスリ、エキサイゼリの成長などが観察されるなど、ほかの植物でも変化がわかりやすいものが増えてきました。

サクラソウの花 |

サクラソウの群落 |

ノウルシが開花して黄色い自生地 |

ジロボウエンゴサクの花 |

ヒキノカサの花 |

ミツバツチグリの花 |

カキドオシの花 |

ヒロハハナヤスリ |

エキサイゼリ |
3月14日
3月2日
自生地の広い場所で、開花したアマナの群落がみられるようになってきました。
天気の良い日にはよく開いた花がご覧いただけます。一緒にヒロハノアマナも開花しているようです。
ノウルシも早いものは開花が始まっています。この時期は茎の先に花が密集していますが、次第に枝が広がっていきます。
サクラソウの開花はまだ先ですが、自生地各地で芽吹いたり、葉が伸びてきている様子が見られます。
|

アマナの群落
|
|

アマナの花
|

ヒロハノアマナの花
|
|

ノウルシの花
|

サクラソウの芽吹き
|
2月21日
今年も開花期に向けてサクラソウ自生地の様子をお知らせしてまいります。
多くのノウルシが芽吹きを始め、サクラソウもあちらこちらで芽吹きを見られるようになってきました。
ヒロハノアマナや、フキなど、開花の早い植物はすでに咲き出しているものがあります。
|

サクラソウの芽吹き
|

ノウルシの芽吹き
|
|

ヒロハノアマナの開花
|

フキの開花
|
交通案内
- バス JR浦和駅西口から:国際興業バス「志木駅東口」行き、「さくら草公園」下車すぐ。
- バス 東武東上線志木駅東口から:「浦和駅西口」行き、「さくら草公園」下車すぐ。
- 電車:JR武蔵野線西浦和駅下車、徒歩約20分。
- 車:国道17号(新大宮バイパス)田島交差点から志木方面へ約1.5km、秋ヶ瀬橋手前の信号を右折。ヘリポート駐車場の看板の先を左折。
- 桜草公園住所:さいたま市桜区大字田島3542-1
見学の際のお願い
- 自生地の動植物は採取しないでください。
- 柵に上がったり、中に入るのはやめましょう。三脚などの機材も柵の中に入れないでください。
- ごみは持ち帰りましょう。
- 観察路へのバイク・自転車などの乗り入れや、ペット同伴での立入りはご遠慮ください。