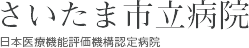ページの本文です。
感染症科専門研修概要
研修目標
初期臨床研修および後期臨床研修で身につけた基本的な診療能力を前提とし、内科医に求められる感染症関連の知識や検査手技を習得する。
感染症診断に関しては、各種感染症を引き起こす代表的な病原微生物について理解すること、病原微生物を特定するための検査法について理解することが求められ、グラム染色やチール・ネールゼン染色などの基本的な検査法については自分自身で実施できるようになることが望ましい。また、検査室に導入された遺伝子解析装置や質量分析装置の特性についても理解する。感染症治療に関しては、抗微生物薬の種類や特徴について理解し、各症例の病態に応じて適切な抗微生物薬を選択できること、抗微生物薬投与以外の治療法について理解することが求められる。各種感染症の予防法や、院内感染防止のための基本的方策について理解することも目標とする。
当科の特徴
当院は、さいたま市内で唯一の第二種感染症指定医療機関であり、感染症法に規定された二類感染症の患者さん(疑似症例を含む)が地域で発生した際に、その診療を担当している。二類感染症以外でも、デング熱やマラリアなどの輸入感染症に罹患した可能性がある患者さんを受け入れており、的確な診断と治療が行えるよう体制を整備している。
国内でも発生頻度の高い感染症(敗血症、尿路感染症、肺炎、急性ウイルス感染症など)や、原因が判然としない発熱・炎症反応高値を認める患者さんについては、院内全科から相談を受け付け、併診を行っている。
また看護師、薬剤師、臨床検査技師とともに感染対策チーム(ICT)と抗菌薬適正使用支援チーム(AST)を組織し、院内感染対策活動と抗菌薬適正使用支援活動に従事している。
スタッフ紹介
| 氏名 | 役職 | 資格等 |
|---|---|---|
| 川田 真幹 | 部長 | 日本内科学会総合内科専門医・指導医 日本感染症学会感染症専門医・指導医 日本化学療法学会抗菌化学療法指導医 ICD制度協議会インフェクションコントロールドクター |
| 小林 竜也 | 医長 |
日本内科学会総合内科専門医・指導医 日本感染症学会感染症専門医 日本化学療法学会抗菌化学療法認定医 ICD制度協議会インフェクションコントロールドクター |
施設認定
- 日本感染症学会認定研修施設
研修内容
輸入感染症(疑似症例を含む)の症例や、院内全科からの相談症例について、感染症科スタッフの指導のもと、診療にあたる。
また血液培養が陽性となった症例、特定抗菌薬(カルバペネム、抗MRSA薬)の処方が7日を超えた症例、 薬剤耐性菌が検出された症例、ほか院内感染対策上問題となる病原微生物(クロストリディオイデス・ディフィシル、インフルエンザウイルス、ノロウイルス、SARS-CoV-2等)が検出された症例については全例把握し、必要に応じて感染症科スタッフとともに診療支援を行う。
検査室において、微生物検査の基礎的知識や手技を習得し、遺伝子解析装置や質量分析装置の特性についても理解する。
毎週行われるICT/ASTミーティングと院内ラウンド(火曜日午後)、症例検討会(木曜日午後)で議論にも参加する。
感染症関連の学会に参加し、専門性の向上を図る。また、感染症関連の学会や学術誌で論文発表・症例報告を行う。
更新日 令和7年4月1日