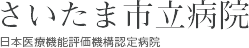ページの本文です。
循環器内科専門研修概要
研修目標
研修終了時に以下を体得していることが目標となる。
・患者さんの病態、人生のステージに応じた医療を家族、コメディカルを含めたチームとして考える姿勢
・専門研修終了後の医師としてのキャリアプランを自分で描けること
・内科医としての臨床推論能力、他科と連携して診療にあたる能力
・循環器救急疾患に対して一人で初期対応が可能となること
・循環器疾患の慢性期管理、外来管理
当科の特徴
当院はさいたま市で唯一の公立病院であり、また中核病院として特に急性期医療に力を入れている。循環器内科は急性心筋梗塞、心不全、急性大動脈解離等、緊急に処置を必要とする疾患を担当し24時間体制で対応している。年間冠動脈カテーテル治療を150~200件(うち緊急が80~100件)、カテーテルアブレーションを80~100件施行している。
循環器内科は一般床の6A病棟固有床を中心として、ICU/HCUといった集中治療室で入院診療を行っている。当科には冠動脈疾患、心不全の他にも不整脈、肺塞栓症、感染性心内膜炎、心タンポナーデ等多様な循環器疾患患者が入院する。不整脈患者に対しては電気生理学的検査及びカテーテルアブレーションを行い、必要に応じて恒久的ペースメーカ移植術や植込み型除細動器(ICD)移植術・両心ペーシング機能付き植込み型除細動器(CRT-D)移植術を行っている。
循環器疾患の診療では心臓血管外科との連携が重要と考えている。ハートチームとして合同カンファレンスを適宜行い、常に風通しの良い診療を心がけている。
突出した症例数を誇る施設ではないが、心不全、冠動脈、不整脈、エコーを含めた画像診断、集中治療、肺循環、先天性心疾患など各分野に経験のある専門家がそろっており、循環器科医としての最初の数年間で幅広い循環器疾患を経験し、臨床の基礎体力を養うには最適な施設だと考える。女性医師、基礎、臨床研究の経験者、地域医療に興味のある医師など多様なバックグラウンドの指導医がおり、それぞれの専攻医の人生、キャリアプランの実現をサポートしていく。
スタッフ紹介
| 氏名 | 役職 | 資格等 |
|---|---|---|
| 武井 眞 | 部長 | 日本循環器学会認定循環器内科専門医 日本内科学会認定総合内科専門医 日本集中治療医学会認定集中治療専門医 日本人類遺伝学会認定臨床遺伝専門医 日本心血管インターベンション治療学会認定医 医学博士 |
| 藤澤 大志 | 科長 |
日本内科学会認定内科医 日本内科学会認定総合内科専門医 日本循環器学会認定循環器専門医 日本不整脈心電学会認定不整脈専門医 |
| 勝木 俊臣 | 医長 | 日本循環器学会認定循環器専門医 日本内科学会認定内科医 リードレスペースメーカー植え込み術認定医 |
| 中澤 直美 | 医長 | 日本循環器学会認定循環器専門医 日本内科学会認定内科医 日本周術期経食道心エコー(JB-POT)認定医 日本心エコー図学会SHD心エコー図認定医 日本臨床検査医学会認定臨床検査専門医 日本臨床検査医学会臨床検査管理医 日本超音波医学会認定超音波専門医 |
| 今枝 昇平 | 医長 | 医学博士 日本内科学会認定内科医 日本循環器学会専門医 日本心血管インターベンション治療学会(CVIT)認定医 日本経カテーテル心臓弁治療学会TAVR実施医(SAPIENシリーズ) 日本経カテーテル心臓弁治療学会TAVR指導医(SAPIENシリーズ) 日本経カテーテル心臓弁治療学会TAVR実施医(CoreValveシリーズ) |
| 梶野 了誉 | 医長 | 日本内科学会内科専門医 日本循環器学会認定循環器専門医 日本心血管インターベンション治療学会(CVIT)認定医 日本経カテーテル心臓弁治療学会TAVR実施医(SAPIENシリーズ) 日本経カテーテル心臓弁治療学会TAVR指導医(SAPIENシリーズ) 日本周術期経食道心エコー(JB-POT)認定医 日本心エコー図学会SHD心エコー図認定医 |
| 渡辺 雄也 | 医師 |
研修内容
プログラムにより当院での研修期間、年度が異なるため、以下は3年目を当院で内科研修、4年目を連携施設、5年目を当院で循環器専門研修を行ったと仮定した場合のモデルケースであり、症例数は当院での2年間(3年目、5年目)での経験数となる。連携施設の実績としては慶應義塾大学、東京大学、さいたま赤十字病院、国立病院機構埼玉病院、埼玉医科大学総合医療センター、東京医科大学などがある。
検査・治療
●非侵襲的検査
胸部X線写真、心電図を的確に読影することは内科医には必須であり、新入院カンファレンス等で担当症例をプレゼンテーションするトレーニングをつむ。 救急外来、病棟の担当症例で心エコー図検査を行う。心機能、壁運動を評価できるようになることが目標。心エコー図検査手技は指導医のチェックを受ける。希望者は日々の心エコー図検討会に参加し多数の検査画像をみることでさらに理解を深めることができる。
●侵襲的検査・治療
臓カテーテル検査、冠動脈インターベンションの適応、方法、術後の管理を理解する。担当する症例の検査、治療では助手を務める。電気生理学的検査、カテーテルアブレーション、恒久的ペースメーカ移植術、植込み型除細動器移植術にも積極的に参加する。
● カテーテル検査
冠動脈造影については研修終了時点で200例を経験し、一人で施行可能となること
冠動脈形成術については研修終了時点で50例を上級医の指導の下術者として施行すること
右心カテーテル検査を一人で遂行し、結果について解釈可能となること
● 心臓超音波検査、運動負荷心電図検査を含めた生理学的検査
研修期間中に生理検査室において各種検査を専従して行う期間を設ける。
経胸壁心臓超音波検査については自己にて判読、評価が可能となること。
経食道超音波検査については30例を施行し、基本的な評価が可能となること。
心肺運動負荷試験、トレッドミル運動負荷試験について自己にて検査を施行し、結果の解釈が可能となること。
● CT/MRI/RI検査
当院では冠動脈CT、造影心臓MRI検査、各種心筋シンチグラム検査が施行可能である。専属の読影研修は現状行っておらず、自己担当症例の検査を中心に読影を学ぶ。
● 外来/他科コンサルテーション
3年目には循環器内科ローテーション中に指導医とともに外来初診、他科コンサルテーションを担当する。5年目には自己の初診外来を担当する。
病棟
入院患者の担当医として指導医のもとで患者治療にあたる(担当患者数約8人前後)。毎朝のミーティング、新入院カンファレンス、心カテカンファレンス、回診等により診療責任者のチェックを受ける。循環器抄読会では分担して世界の優良な文献から疾病・臨床試験への理解を深めプレゼンテーションをおこなう。
病棟担当医として患者の診療にあたる。診療はチーム制(主治医を含め2-3名)で担当症例数は10-15例程度となる。担当症例の検査、手技は基本的に担当専攻医を優先して術者とする。病棟ローテーション中はカンファレンスでの症例発表など指導医とディスカッションを行う機会を設ける。
当直
内科専攻医のー員として内科初診外来、救急外来当番、月3~4回の内科当直を分担する。
内科専攻医も指導医と共に緊急心臓カテーテル治療に参加する。
3年目内科ローテーション時は内科救急外来当直を月に4回程度担当する。5年目には内科当直と併せて循環器内科当直も担当する。当直明けはチームに申し送りを行い、遅くとも昼までの可及的速やかな帰宅を奨励している。そのほか、夜間、休日の緊急カテーテル検査などの際のオンコールを担当する。
学会、研究会など
指導医のもと症例報告等の演者として内科学会地方会、日本循環器学会地方会等に参加し、論文にまとめることが要求される。自分が経験した症例について詳しく調べ、他者に説明することにより自らの知識や理解を深めることができる。
3年目に日本内科学地方会での発表を行う。5年目には日本循環器学会総会での発表を目標として臨床研究、症例報告の準備を行う。そのほか各種研究会などで発表の機会を設ける。指導医には英語論文指導の経験者が複数名おり、希望すれば専門研修中の英語論文の執筆も可能である。
研修終了後
研修終了後は慶應義塾大学をはじめとした大学病院、さいたま市内、埼玉県内の各医療機関への紹介が可能である。
更新日 令和7年4月1日